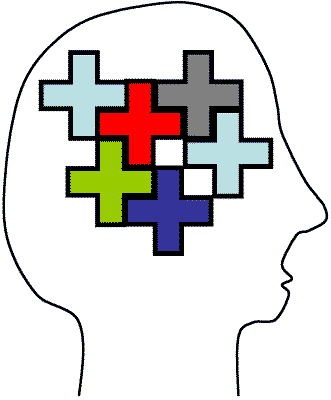「実験的アプローチ」と「モデルベースアプローチ」は,認知科学の主要な研究方法の柱である。特に,モデルベースアプローチは,伝統的な心理学に対して認知科学を特徴づける重要な性質であり,このアプローチの成立が,人間の知の探求に新たな時代を開いたと言っても過言ではない。実際,認知科学におけるThe Prizeと言ってもよいRumelhart Prizeの10人の受賞者のリスト(ここ
)を眺めると,その中の少なくとも8名までが,モデルベースアプローチにその研究の主軸を置いた研究者であることを確認することができる。ここでは,両アプローチの比較を行いつつ,認知科学の関心,方法論に関する導入を行う。
Miwa, K. (2008). A cognitive simulator for learning the nature of human problem solving. Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence, 23, pp. 374-383.
第2回
発見
科学者が法則を発見し,理論を構築するプロセスには,どのような知識や方略が関わるのかということが,ここでのメインテーマである。科学的発見のプロセスには,仮説形成と仮説検証という2つのフェーズが存在する。ここでは,この2つのフェーズの相互作用として科学的発見を捉え,「実験室的研究」,「モデルベースの研究」という2つの観点から発見に関わる研究を紹介する。
Note
References
-
Klayman, J., & Ha, Y. (1987). Confirmation, disconfirmation and information in hypothesis testing. Psychological review, 94, pp. 211-228.
-
Klahr, D. (2002). Exploring Science: The Cognition and Development of Discovery Processes. MIT Press.
-
Miwa, K. (2004). Collaborative discovery in a simple reasoning task. Cognitive Systems Research, 5, pp. 41-62.
-
三輪和久 (2000). 共有認知空間の差異が協調的発見過程に与える影響, 人工知能学会論文誌,15, 854-861.
-
冨田隆・三輪和久 (2002) 発見における有効な仮説検証方略と協同の効果,認知科学, 9(4), 501-515.
第3回〜4回
洞察
誤った思いこみ,先入観から脱することができずなかなか答に気づけない。その一方で,わかる時には前触れなく突然解が思いつく。わかてしまえば何でこんな簡単なことに気づかなかったのかがわからない―。そのような現象は「洞察」と呼ばれ,人間の発見や創造に深く結びついていると言わる。本研究では,問題解決における洞察を,実験的アプローチとモデル的アプローチの両面から検討する。
Note
References
-
Terai, H., & Miwa, K. (2006) Sudden and Gradual Processes of Insight Problem Solving: Investigation by Combination of Experiments and Simulations. Proceedings of 28th annual meeting of the cognitive science society, 834-839.
-
三輪和久・松下正法 (2000). 発見における心的制約の緩和過程.認知科学, 7, 152-163.
-
寺井仁・三輪和久・古賀一男 (2005). 仮説空間とデータ空間の探索から見た洞察問題解決過程. 認知科学, 12, 74-88.
-
三輪和久 (2009) 飛躍を伴う発見における潜在的意識の関与:洞察問題解決研究からの知見. 計測と制御, 48, pp. 33-38.
第4回〜5回
異視点コミュニケーション
2人の人間が,同じものを見ているにも関わらず,全く異なった事実を認識しているといった状況が生じることは少なくない。このような状況では,コミュニケーションの齟齬が生じたり,議論がかみ合わなかったりといった否定的な側面が現れると同時に,時にその相互理解の過程を通して,新しいものの見方が生まれたり,創造的飛躍が現する可能性が現れたりする。本研究では,そのような相互作用を「異なる視点に基づく協同問題解決」と捉え,新たな課題を考案してそのプロセスを検討した。これらの問題は,異文化間コミュニケーションや分散認知の基礎研究としても重要である。
Note
References
-
林勇吾・三輪和久・森田純哉 (2007) 異なる視点に基づく協同問題解決に関する実験的検討. 認知科学, 14, 604-619.
-
Hayashi, Y., & Miwa, K. (2009). Prior experience and communication media in establishing common ground during collaboration, Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society, pp. 526-531.
-
Hayashi, Y., & Miwa, K. (2009). Cognitive and Emotional Characteristics of Communication in Human-Human/Human-Agent Interaction, LNCS, 5612, pp. 267-274.
第5回〜第7回
論理
人間の思考の土台にある論理の体系として,自然演繹を学ぶ。
Note
References
-
戸田山和久著. 論理学をつくる. 名古屋大学出版会.
第8回〜第9回
創造性
1人で考えるよりも2人で考えるほうが,より独創的なアイデアが生まれるのか。生まれるとすれば,なぜ2人で考えと独創的なアイデアが生まれるのか。実験を通して,創造的アイデア生成に関する協同の効果を検討する。
創造的活動には,アイデアを考える心的過程と,そのアイデアを物理的に具体化する外的過程という2つの段階が存在する。この研究では,その2つの段階の相互作用という観点から創造活動を捉え,熟達者と初心者の創造プロセスを比較し,エキスパートの創造過程の特質を明らかにする。実験の題材には,Mindstormsというロボット制作キットを用いた。
Note
References
-
Ronald A. Finke, et al. 小橋 康章 (翻訳) 創造的認知―実験で探るクリエイティブな発想のメカニズム. 森北出版.
-
石井成郎・三輪和久 (2001,6) 創造的問題解決における協調認知プロセス, 認知科学, Vol.8, No.2, 151-168.
-
石井成郎・三輪和久 (2003) 創造活動における心的操作と外的操作のインタラク ション, 認知科学, 10, 4, 469-485.
第10回
思考スタイル
Stanbergらの提唱した思考スタイルによると,人間は,その思考の好みとして,立案,順守,評価という3つの型を持つとされる。本研究では,異なった思考スタイルを持つ3人が創造的活動を行うことによって,そこにどのような相互作用が生まれるのかを実験的に明らかにする。
Note
References
-
Robert J. Sternberg. 松村・比留間 (翻訳) 思考スタイル―能力を生かすもの. 新潮社.
-
Ichihara, T., Miwa, K., & Ishii, N. (2008). Analysis of Collaboration in Creative Problem Solving Based on Thinking Styles. The Journal of Information and Systems in Education. 6. pp. 5-16.
第11回〜第12回
プロダクションシステムモデリング
最終課題